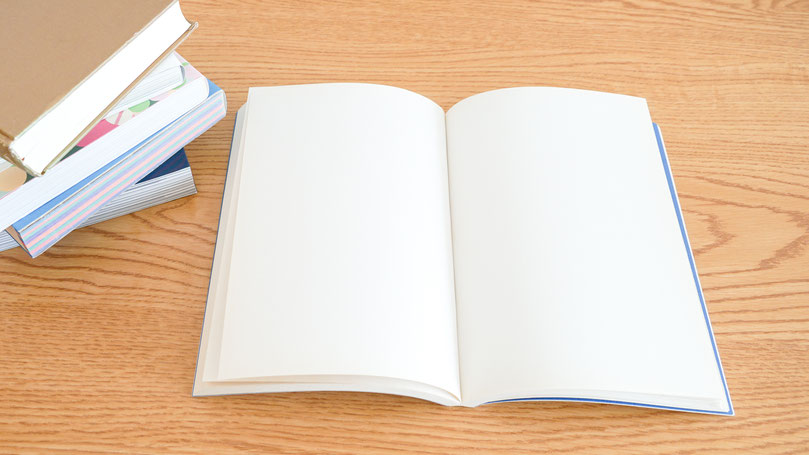1.工業地帯と工業地域の違い
工業地帯と工業地域。
結論からいうと、この2つの言葉に明確な違いはありません。
それぞれの言葉は慣習的につけられたもので、かつては京浜、中京、阪神、北九州が四大工業地帯と呼ばれていました。
すなわち工業生産額の多いところです。
そしてそれ以外を全て工業地域と呼んでいました。
現在は、北九州の生産が減少したので三大工業地帯と呼んでいます。
地位が低下した北九州は、「北九州工業地域」と呼ぶ場合と、慣習的に現在でも「北九州工業地帯」と呼ぶ場合があります。
2.工業地帯と工業地域の具体例
現在、三大工業地帯と呼ばれているのは以下の3つです。
■京浜工業地帯
東京都から神奈川県にかけて、東京、川崎、横浜などの工業都市があります。
■中京工業地帯
愛知県から三重県北部にかけて、豊田、名古屋、東海、四日市などの工業都市があります。
■阪神工業地帯
大阪府から兵庫県にかけて、堺、大阪、尼崎、神戸などの工業都市があります。
この3つの中でももっとも工業生産額の多いのは、豊田の自動車工業を中心とする中京工業地帯です。
都道府県別の工業生産額でも、第1位は愛知県となっています。
北九州も含めてかつて四大工業地帯と呼ばれていたころ、京浜から北九州を結ぶ帯状の地帯は太平洋ベルト地帯と名付けられました。
鉄鋼業や石油化学工業を中心とした重化学工業が発達し、まさに日本の工業の中心であったのです。
これらの工業地帯に続いて、1960年代の高度経済成長期には、倉敷(水島)などの瀬戸内、浜松などの東海、市原などの京葉といった工業地域が、太平洋ベルト地帯を埋めるように発達していきました。
このような工業地域やそのほかの地域も含めて、原料の輸入に便利な臨海部に次々とコンビナートがつくられました。
※コンビナートとは
効率的な工業生産を行うために、石油精製や化学合成などの事業所をひとつの企業として、ひとつの地域に集めたもの。
そしてほかの先進国と同様に鉄鋼業などが停滞してくると、日本の工業の中心は自動車工業や先端技術産業に移っていきました。
この流れにともない、関東内陸(北関東)工業地域のように新しい工業地域も誕生しました。
また原料や製品が軽量、小型で輸送しやすいという利点から、空港や高速道路沿いにIC関連工場が多くつくられました。
これらはシリコンアイランド(九州)や、シリコンロード(東北)と呼ばれていますが、工業地域とは呼ばれていません。
・工業地帯と工業地域に明確な違いはない。
・京浜・中京・阪神が工業地帯、それ以外はすべて工業地域。
次回は「山地と山脈と高地」です!
詳しく「札幌自学塾」を知りたい方は、ホームページを参照してください! こちらをクリック>>
無料体験・申し込みは、「お問い合わせ欄」からメールしてください! こちらをクリック>>